休日勤務が多い工場の特徴10選!工場選びのコツを徹底解説
2024年11月29日

工場勤務を考える際、勤務形態はとても重要なポイントです。
特に「休日勤務が多い工場」には独特の特徴があります。
それを知らずに就職してしまうとプライベートの時間が確保できず、ストレスを抱える原因になるかもしれません。
本記事では休日勤務が多い工場の特徴や、それに適応するための工場選びのコツを徹底解説します。
さらに、実際に休日勤務を経験した2名の体験談を交えながら、その現実を深掘りしていきます。
休日勤務が多い工場の特徴10選

① 繁忙期が明確にある
繁忙期のある工場では、休日勤務が必要になることが多々あります。
例えば食品加工の工場では、クリスマスや年末年始などのイベントに向けて製品の需要が高まります。
この時期には通常よりも生産量を増やさなければならず、休日に稼働することが必要となる場合があります。
また物流関連の工場でも、ネットショッピングのセール時期や連休前後に注文が集中するため、人員不足を補うために休日出勤が頻発します。
こういった工場では、事前に「繁忙期には休日勤務がある」と説明される場合もあれば、実際に働き始めてからその頻度の多さに気づくこともあります。
② 24時間操業のシフト制を採用
製造ラインを止めることができない工場では、24時間体制のシフト勤務が一般的です。
これらの工場では稼働時間を最大化するため、週末や祝日も通常どおり稼働するケースが多く、結果として休日勤務が発生しやすくなります。
シフト制で休日を調整する仕組みがあっても全員が休む日がなく、代わりに自分が出勤することになることがよくあります。
特に自動車部品や半導体関連の工場など、製造ラインの停止が大きなコストにつながる業界では、この傾向が顕著です。
③ 製品の賞味期限や鮮度を重視
食品や医薬品などの工場では、製品の品質を保つために一定のペースで製造を続ける必要があります。
特に生鮮食品を扱う工場では、商品の賞味期限が短いため在庫を抱えすぎないように計画的に製造を行う必要があります。
しかし、予期せぬ需要の増加や天候の影響で原材料の供給に遅れが生じた場合には、休日に製造を調整しなければならないこともあります。
こうした状況下では、休日でもフル稼働を求められることが多いのです。
④ 顧客の緊急対応が必要な場合がある
工場の中には顧客から急ぎの発注があった場合、休日であってもすぐに対応することが求められる場合があります。
特に、機械部品や精密機器の製造を行う工場では、納期厳守が信頼関係を左右するため顧客の要望に応えるために休日出勤が必要となることがしばしばあります。
こうした場合、特定のプロジェクトが終わるまで休日勤務が続くことも珍しくありません。
⑤ 人員不足が慢性的に起こっている
労働力が不足している工場では、少ない従業員で業務を回す必要があるため一人当たりの負担が増え、休日勤務が常態化しやすくなります。
特に、離職率の高い工場や派遣社員が多い職場では、人員の補充が間に合わず、休日にも出勤を求められるケースが多く見られます。
慢性的な人手不足は、働く側にとっても精神的な負担が大きくなる原因となります。
⑥ 天候に左右される業界に属している
天候に大きく左右される産業、例えば農業関連や建材製造の工場では、悪天候による遅れを取り戻すために休日に稼働することがあります。
さらに、予期せぬ天候変化に対応するため、スケジュールが急に変更されることもあります。
このような工場では、休日に働く柔軟性が求められることが多いです。
⑦ 納期が厳しいプロジェクトがある
受注生産型の工場では、顧客からの注文に応じて製造を行います。
納期が厳しいプロジェクトを抱えている場合、生産ラインの稼働が追いつかないときに休日勤務で対応することがあります。
こうした工場ではプロジェクトごとに繁忙期が発生し、その都度従業員に大きな負担がかかることがあります。
⑧ 設備のメンテナンス日を休日に設定
生産ラインを止められない工場では、設備の点検やメンテナンスを通常の稼働時間外、つまり休日に行うことが一般的です。
この場合、メンテナンス作業を担当するスタッフやその監督を行う社員が休日に出勤する必要があります。
特に、製造機械が高度化している現代の工場では、専門的なスキルを持つスタッフが求められるため、休日勤務が避けられないことがあります。
⑨ 派遣社員が多い工場
派遣社員が多い工場では、契約内容によって休日勤務が設定されていることが多く、これが正社員や他のスタッフの休日勤務にも影響を与えることがあります。
シフトの調整が難航する場合、休日に出勤を余儀なくされることもあります。
⑩ 特殊な製造工程を持つ工場
製造工程の中に特定のスキルや資格が必要な工程が含まれる場合、その作業を担当できる社員が限られていることがあります。
こうした場合、特定の社員に負担が集中し、休日に出勤する必要が生じることがあります。
工場選びのコツ

休日勤務が多い工場の特徴を理解したら、自分にとって最適な職場を選ぶためのコツを押さえましょう。
① 求人情報を詳しく確認する
求人情報には、その工場の勤務形態や働き方のヒントが隠されています。
「シフト制」「交代制」「繁忙期に出勤あり」などの記載がある場合、休日勤務が発生する可能性が高いです。
また、給与が高い場合はその分休日勤務が求められる可能性も考えられます。
面接時には、具体的な休日の取り方や休日勤務の頻度について質問することが重要です。
② 従業員の口コミを調べる
インターネット上の口コミサイトや掲示板では、実際に働いた人の生の声を確認できます。
例えば、「残業が多い」「休日出勤が頻繁」などの記載があれば、それを参考に工場の実態を把握できます。
特に、休日の過ごし方や職場の雰囲気について言及している口コミは貴重な情報源です。
③ 工場見学を活用する
多くの工場では、入社前に職場見学を行うことができます。
見学の際に、スタッフの様子や生産ラインの稼働状況をチェックし、実際の働き方をイメージすることが大切です。
また、質問を通じて具体的な勤務形態や休日の過ごし方について確認しましょう。
④ 業界特性を考慮する
工場の業界によって、休日勤務の頻度が大きく異なります。
例えば、食品業界や物流業界は繁忙期がある一方で、精密機械や自動車関連の工場は比較的安定した勤務形態を持つことが多いです。
自分のライフスタイルに合った業界を選ぶことが、働きやすさにつながります。
⑤ 自分のライフスタイルを見直す
休日勤務が発生しても対応できる生活リズムを持っているか、家族や友人との時間をどの程度優先したいかなど、自分自身の価値観や生活スタイルを明確にすることが重要です。
これにより、無理なく働ける職場を選べるようになります。
休日勤務を経験した方の体験談

体験談①:忙しさに疲れた元工場勤務者の話
私が以前働いていた食品工場はクリスマスや年末年始が特に忙しく、ほぼ毎週休日出勤でした。
当時はお金が必要だったので頑張っていましたが、体力的にはかなり厳しかったです。
特に同じペースでライン作業を続けるため、疲労が蓄積していくのが辛かったですね。
今思えば、事前にしっかり工場の特徴をリサーチしていれば、違う選択をしていたかもしれません。
(30代男性)
体験談②:自分に合う工場を見つけた経験
以前、部品加工の工場で働いていた頃、顧客からの急ぎの注文が多く、休日出勤が頻繁でした。
ただ、その後転職して自動車部品を製造する工場では事前のスケジュールがしっかりしており、休日勤務がほとんどありませんでした。
同じ工場勤務でも、職場によってこれほど環境が違うとは驚きです。
現在はプライベートも充実しており、満足しています。
(20代女性)
まとめ:求人の特徴やライフスタイルに合った選択を!
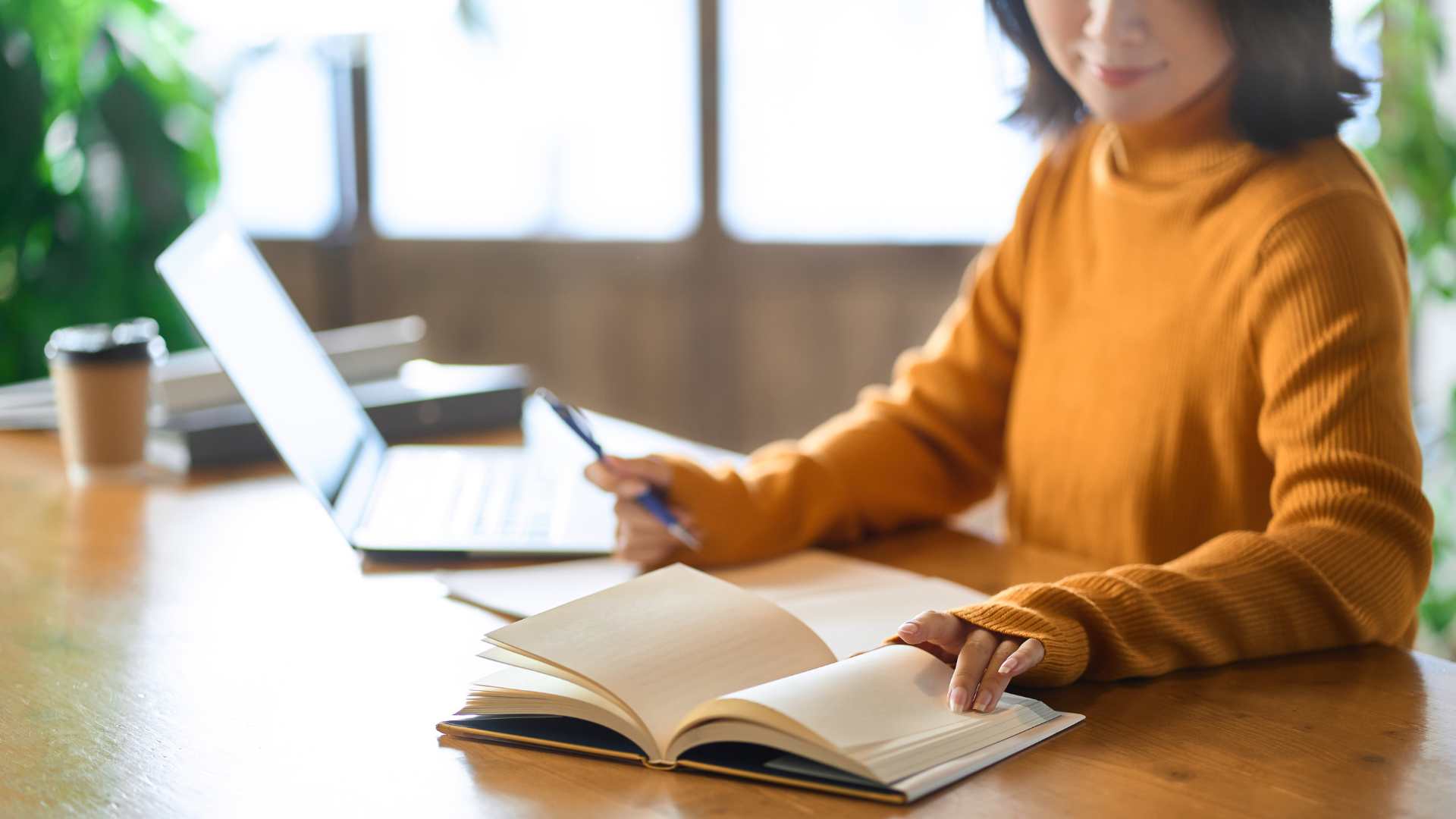
「休日勤務が多い工場」は、繁忙期や業界特性により発生しやすいものです。
事前にその特徴を理解し自分のライフスタイルに合うかどうかを見極めることが、満足度の高い職場を選ぶための鍵となります。
体験談からも分かるように、リサーチの有無で大きく環境が変わってしまうのです。
この記事を参考に、納得のいく工場選びをしてくださいね。
ライター情報
佐保 健太郎
「住み込み」に特化した求人サイトのライフジョブを運営。 リゾートバイトや出稼ぎ求人、寮付きの求人をご紹介しています。 学生時代からリゾートバイトや期間工の仕事を複数経験。 出身は兵庫県、特技はお菓子作り。









